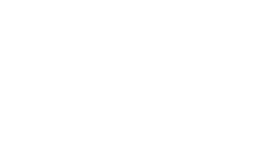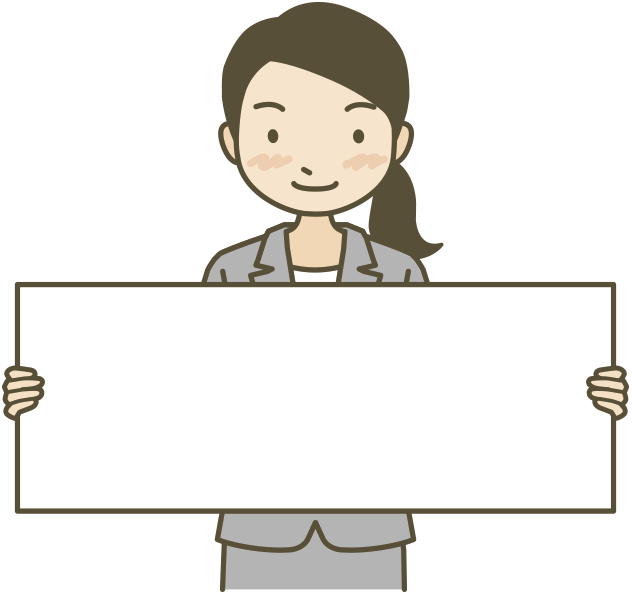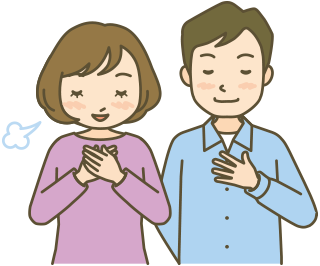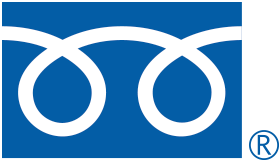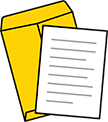会葬のマナー/Q&A


-
お葬式に給付金が出るのですか?
故人が「国民健康保険加入者」、または「社会保険加入者」の場合、所定の手続きを行うと葬祭費用の給付金を受け取れる制度がございます。
お葬式を終えられた後、期日内に申請を行わないと受け取れないので忘れないように申請を行う事をおすすめいたします。
下記を参考に葬儀後に申請をおこなってください。
【故人が国民健康保険に加入していた場合】
- ・葬祭費として 3~7 万円程度が支給されます。
※自治体によって金額は異なります。
各市区町村役所の国民健康保険課が申請窓口となります。申請の際に必要な物は以下になります。 - ・葬祭費として 3~7 万円程度が支給されます。
※自治体によって金額は異なります。
各市区町村役所の国民健康保険課が申請窓口となります。申請の際に必要な物は以下になります。 - ・葬儀の領収書
- ・故人の国民健康保険証
- ・申請者の印鑑(喪主の場合が多い)
- ・葬祭費の振込先の口座番号
※必要書類は申請先によって異なります。 申請前に直接窓口へご確認ください。
【故人が社会保険に加入していた場合】
- ・埋葬費として一律 5 万円が支給されます。
(健康保険組合によっては独自の補助金制度がある場合がございます)勤務先、または所轄の社会保険事務所が申請窓口となります。
申請の際に必要な物は以下になります。 - ・死亡診断書または埋葬許可証
- ・故人の健康保険証
- ・勤務先事業主による証明書類(申請書類への記入・捺印)
- ・申請者の印鑑
※必要書類は申請先によって異なります。 申請前に直接窓口へご確認ください。国民健康保険の場合、社会保険の場合、どちらも申請期間は死亡日より 2 年間となります。
- ・葬祭費として 3~7 万円程度が支給されます。
-
もしもの時、すぐに必要になるものは何ですか?
医師から受け取る「死亡診断書」は今後の様々な手続きに必要となる重要な書類です。必ず無くさないようにしましょう。その他、各場面ごとに必要なものもありますので、お気軽にご相談下さい。
-
役所への手続きについてはどうすればよいですか?
火葬を行うためには、役所へ死亡届を提出し火葬許可証を取得する必要がありま す。この手続きは弊社で代行することもできますのでご相談ください。火葬許可証は火葬が済んだ後、火葬済みの証印が押されて手元に戻ります。それが埋葬許可証として、後々お墓に納骨する際に必要な書類になりますので大切に保管しましょう。火葬場にもよりますが、収骨容器を覆う桐の箱の中に一緒に納められる傾向がありますので、火葬後に見当たらない時は、まず確認して見ましょう。
-
葬儀費用の注意点は、どんな所ですか?
広告などにある金額だけで比較しないことが大切です。お客様用に見積られた金額ではない場合、実際との差が必ず生じるといっても過言ではありません。特に先に葬儀社が設定したプランでは、「必要なものがすべて含まれます」「追加料金一切なし」などと広告されますが、必要か不要かの判断をお客様が行ったわけではありません。宗教による違いや専門的な部分を端折ってしまうことは後々お客様が恥をかく恐れがあります。専門家である葬儀社にきちんとご相談いただき、ある程度の予算や希望を伝えて、葬儀費用に理解と納得をしながら進めていくほうが良いでしょう。
必要な葬儀費用は、葬儀社のみならず式場・火葬場・車輌・料理・返礼品・お布施など多岐に渡ります。
弊社ではお見積りの段階でお客様のご要望を踏まえてご提案いたしますので、過不足のない最適な金額が算出されます。もちろん、後で膨大な請求をしたりすることもありません。また、予算が心配なときは率直にご相談ください。葬儀費用をできるだけ抑えた形でしっかりとご提案いたします。 -
早朝や深夜でも対応してもらえますか?
24 時間 365 日対応しております。ご葬儀の事ならお気軽にお電話下さい。
0120-77-9876 -
葬儀の日程はどのようなスケジュールになりますか?
葬儀の一般的な日程では、故人様が亡くなった翌日に通夜を行い、翌々日に葬儀と告別式・火葬を行います。いつまでに行わなければいけないというルールはございませんが、なるべく早く行うことが望ましいです。
-
お通夜はいつするものですか?
明確な決まりはありませんが、亡くなった当日の夜に仮通夜を行い、その翌日にお通夜を行います。しかし、実際には火葬場の空き具合、参列者の希望などもございますので、日にちをずらす場合もあります。
-
万が一の時に備えて何を準備していればよいですか?
訃報の際に連絡先のリストの作成をしておくと、いざという時にスムーズです。エンディングノートを書いておくのもおすすめです。
-
納棺の際はどんなものを入れるのが一般的ですか?
「お好きだった食べ物」や「お洋服」を入れられるご家族が多いです。愛煙家の方には「タバコ」を入れることもあります。入れられないものもございますので、詳しくはご相談ください。
-
お葬式ができない日はありますか?
「友引」の日です。友引の日は殆どの火葬場がお休みなので葬儀が行えません。ただし、その日のお通夜は行えます。
-
喪主は誰が行うのが良いでしょうか?
喪主はご遺族で協議して決定します。一般的には故人の配偶者、長男、長女という順番で近い方が務めます。配偶者や子供がないときは親兄弟が務め、高齢などの場合には実務を代役の方がサポートして行われます。迷う時にはご相談ください。ご関係に応じて良い方法をご提案いたします。
ご関係が複雑な場合などは迷われることもあるでしょう。更に喪主と施主は違いがあります。喪主はお葬式の実務的な部分の代表となり、大きな役割としては参列者へのご挨拶・お礼状に名前が印刷される・出棺の時の挨拶などがあげられます。喪主の役割は分担しても行われますし、金銭的な面の代表となる施主を兼ねる場合も多くあります。 -
お寺など、宗教者への連絡はどうすればよいですか?
決まったお寺がある場合には連絡してご都合を聞き、葬儀日程の調整を行わなければなりません。
遠方の場合でも後々を考えて必ず連絡を入れておくと良いでしょう。その時に近くの同じ宗旨の僧侶をご紹介いただける場合もありますので、お寺(菩提寺)が決まっている場合には関係を保つためにも一報が必要です。
決まったお寺などがない場合に弊社では、ご希望に応じて寺院などをご紹介いたします。実際に寺構えがあり、後々の法事のことなども相談できるお寺を厳選していますので安心してご相談ください。 -
親族や関係者への連絡は、いつしたらよいですか?
危篤時は必要と思われる方に連絡します。親戚や関係者には、ある程度お葬式の式場や日程が決まってから連絡を行うと良いでしょう。ご関係によりますので一概に言えない面もありますが、日程などが未定の段階でお知らせをするのは、混乱を招きますので滞りを避けるために調整しましょう。
お知らせを行う際にも、故人の交友関係に漏れがないか注意し、お知らせする箇所
が多い場合には学校、会社、町内会、趣味の会などのグループに分け、各責任者に連絡を回してもらう方式をとるとスムーズに進みます。 -
亡くなった後は、どのような流れになりますか?一般的なものを教えてください。
故人を一度ご自宅にお連れし布団にお寝かせするのが一般的です。病院などから故人を移送する車の手配やご自宅へ安置する人手が必要になります。この時に病院で車を手配してくれる場合もありますが、これをどこかの葬儀社が請負う場合も多く見られます。その後の段取りのこともありますので、葬儀を依頼する葬儀社が決まっている場合には、最初からお任せするとスムーズです。また、住宅事情などで自宅に安置が難しい時は弊社にご相談ください。葬儀会館や安置施設などをご提案いたします。
-
亡くなった後、まずは何をすべきですか?
病院などで亡くなった場合、法律で 24 時間経過するまでは火葬ができないことになっています。
そのため故人の安置場所を取り急ぎ決める流れになり、自宅・斎場・専用施設などが主な候補としてあがります。この時に慌てることなく慎重に対応することが重要です。「一度は自宅に帰してあげたい」「利便性を優先して葬儀会館に直接連れていきたい」など、ご希望がおありでしょう。また、同時にお葬式をどこで行うかなど、全体の流れを通して最適な安置場所を考える必要がありますので、この時には専門的な情報が色々と必要になります。依頼の有無にかかわらず、もしもの時は弊社にご相談ください。
一緒に付添いたいなどのご要望にも応じて最適なご提案をいたします。